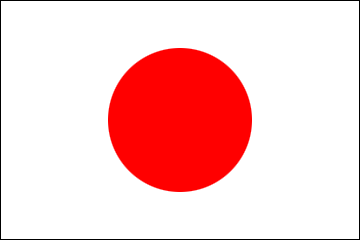領事情報
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載されることになっています。 戸籍に関わる届出(出生届、婚姻届など)は、領事部窓口に届け出て下さい。
戸籍・国籍関係の届出詳細については、外務省ホームページ「戸籍・国籍関係届の届出について」も併せて参照して下さい。
その他、戸籍・国籍手続に関しては、当館領事班(consular@s1.mofa.go.jp)にお問い合せください。
(ご案内する手続)
1.出生届
出生の日から3ヵ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に領事部窓口へ届け出て下さい。
出生児が外国の国籍も併せて取得している場合(例えば、父または母がセルビア(モンテネグロ)国籍である場合等)は、この届出期限内に日本国籍を留保する意志表示(出生届の国籍留保欄に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
必要書類
1.出生届(窓口にも用紙があります)2通
2.出生証明書(Izvod iz maticne knjige rodjenih)2通
※生まれた住所・日時が詳しく記載された公印及び署名オリジナル
3.同和訳文(申請者自身で翻訳、当館でチェック)2通
4.外国人配偶者の旅券コピー及び和訳(申請者自身で翻訳、当館でチェック)2通
2.セルビア及びモンテネグロでの婚姻手続
「日本方式にて婚姻する方法(創設的婚姻届)」と「セルビア(モンテネグロ)方式にて婚姻する方法(報告的婚姻届)」があります。
《日本人同士の場合》
日本方式にて婚姻する場合は下記「婚姻届」を参照
《配偶者の一方が外国人の場合》
セルビア(モンテネグロ)の法律に基づいて、「セルビア(モンテネグロ)方式」にて婚姻することになります。「日本方式」にてセルビア(モンテネグロ)人とセルビア(モンテネグロ)にて婚姻することはできません。
「セルビア(モンテネグロ)方式」で婚姻される場合には、以下を参考に手続きをお進め下さい。
1.婚姻場所
(1)通常は当事者のどちらか一方が住んでいる町の役所(Opstina)になります。
(2)婚姻日当日に当事者および証人が出頭して、婚姻担当の官吏(Maticar)面前で婚姻の宣誓、婚姻書類にサインを行うことにより成立します。
2.婚姻のための必要書類
(1)セルビア(モンテネグロ)の法律に基づいて婚姻をする場合の手続きについては、市役所(Opstina)により若干異なりますので、まず、市役所の婚姻担当の官吏(Maticar)から詳細を確認して下さい。
(2)一般的には、下記の証明書が要求されます。また、戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)など市役所発行の文書に日本官憲の公印アポスティーユ(Apostille)を要求されます。
(3)セルビア(モンテネグロ)での婚姻を進めるにあたり、以下の書類を用意する必要があります。
(ア)出生証明書(当館で発行します。)
(イ)婚姻要件具備証明書(当館で発行します。)
(ウ)旅券
(4)セルビア及びモンテネグロで婚姻が受理された後、当館にて婚姻届を提出いただきます。
※アポスティーユ証明については、当HPの各種証明(https://www.yu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_001_00005.html#article_5)をご確認ください。
3.婚姻届
セルビア(モンテネグロ)方式での婚姻成立日から3か月以内に婚姻届を領事部窓口に提出して下さい。3か月を経過して届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出していただくことになります。
《日本方式による日本人同士の婚姻》
外国にいる日本人同士が婚姻しようとする時は、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届け出をすることによっても婚姻が成立します。
1.必要書類
(1)婚姻届2通(窓口に用紙があります)
※ご提出いただく用紙の大きさはA3です。
※本籍地を夫または妻の本籍地と別の市区町村に新しく設ける場合は、婚姻届が2通必要となります。
※新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合は関しては、当館領事班(consular@s1.mofa.go.jp)にお問い合せください。
(2)婚姻証明書
(3)婚姻証明書和訳文(翻訳者名を明記)
(4)旅券等身分証明書
《配偶者の一方が外国人の場合》
1.必要書類
(1)婚姻届2通(窓口に用紙があります)
(2)婚姻証明書
(3)婚姻証明書和訳文(翻訳者名を明記)
(4)外国人配偶者の国籍を証明する書類(国籍証明書は発行日の新しいもの、パスポートはオリジナル)
(5)外国人配偶者の国籍を証明する書類の和訳文(翻訳者名を明記)
2.注意事項
(1)婚姻から3か月以上経過している場合には「遅延理由書」の提出いただく必要があります。
4.離婚届
セルビア(モンテネグロ)方式での離婚判決確定日から3か月以内に離婚届を領事部窓口に提出して下さい。3か月を経過して届け出る場合には、当館領事班(consular@s1.mofa.go.jp)にお問い合せください。
1.必要書類
(1)離婚届2通(窓口に用紙があります)
(2)離婚判決確定、同判決謄本
(3)離婚判決確定、同判決謄本の和訳文(翻訳者名を明記)
(4)遅延 理由書(署名及び押印が必要)
※日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出をする義務があります。10日経過後に届出をされる場合は、遅延理由書を離婚届と同じ通数作成してください。なお、被告の場合には、判決確定後10日経過後に届け出てください。この場合には遅延理由書は必要ありません。